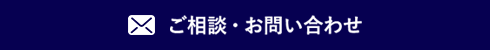コラム
【2025年6月施行】企業向け熱中症対策が義務化!対応方法と罰則を解説
2025年6月1日から、企業における「熱中症対策」が義務化されることをご存じでしょうか。厚生労働省による労働安全衛生規則の改正により、作業環境や気温に合わせた熱中症予防措置を講じることが、すべての事業者に求められるようになります。これにより、適切な対策を講じなかった場合には罰則が科される可能性もあるため、企業は早急な対応を取ることが必須です。
本記事では、熱中症対策義務化の背景や改正内容、企業が取るべき具体的な対策、違反時の罰則までをわかりやすく解説します。従業員の安全と健康を守るために、ぜひ最後までご覧ください。
2025年6月1日から、企業は「熱中症対策」を義務付けられることをご存じでしょうか。厚生労働省の労働安全衛生規則が改正され、すべての事業者は作業環境や気温に合わせた熱中症予防措置を講じることが求められます。この改正により、適切な対策を講じない場合、罰則が科せられる可能性もあるため、企業は速やかに対応する必要があります。
この記事では、熱中症対策義務化の背景や改正内容、企業が実施すべき具体的な対策、違反時の罰則について分かりやすく説明します。従業員の安全と健康を守るために、ぜひ最後までご覧ください。
2025年6月より熱中症対策義務化される?
2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正に伴い、企業における熱中症対策が法律で義務づけられることとなりました。これまで「努力義務」とされてきた対応が明確に義務づけられる形となり、違反があった場合には罰則の対象となることが大きな変更点です。
この改正の背景には、毎年のように発生している作業中の熱中症による労働災害の深刻化があります。特に、建築現場や工場など、高温多湿な場所で働く人々の間で、重篤な症状や死亡事故が後を絶たず、厚生労働省は「作業者の命を守る」ための対策強化に踏み切りました。
対象となるのは、作業環境が「高温状態」にある職場です。たとえば、気温が31℃以上、あるいは暑さ指数(WBGT値)が28を超える条件下で、連続して1時間以上、もしくは1日4時間以上作業を行うケースが該当します。
企業は、作業環境の温度や湿度を適切に把握し、必要な予防措置を講じたうえで、従業員に対して熱中症の危険性や対応策についての教育・周知を行うことが求められます。これにより、職場内の安全衛生管理体制が一層問われることになります。
熱中症対策の法的義務
改正された労働安全衛生規則により、高温環境で作業を行う職場では、事業者が熱中症の防止策を講じることが法的に求められるようになりました。ここでは、企業が具体的に講じなければならない義務内容について解説します。
暑さ指数(WBGT値)の定期的な測定と職場環境の確認
はじめに企業が行うべき基本対応として、作業現場の暑さに関する状況を正確に把握することが挙げられます。
具体的には、現場の気温や湿度、輻射熱などを総合的に評価する「暑さ指数(WBGT値)」を測定し、その数値が28℃以上、または気温が31℃を超える場合には、労働者を守るための具体的な対策を講じる必要があります。このように、単なる気温だけでなく湿度や輻射熱も考慮したリスク評価が求められます。
危険を未然に防ぐための対策立案と従業員への共有
万一の事態に備え、作業中に熱中症を疑う症状が出た場合の「重篤化を防ぐための対応手順」の策定と周知も義務となります。これは、倒れた従業員への初期対応や救急要請の流れを事前にマニュアル化し、現場で誰もが迅速に対応できる体制を整えることを意味します。
作業員向けの研修実施と報告・対応体制の整備
作業者に対する教育も不可欠です。熱中症のリスク、初期症状、対処法を理解させるとともに、体調不良を感じた際にすぐに報告できる体制を整える必要があります。衛生委員会での議論や安全衛生教育などを通じて、継続的な周知が求められます。
このように、今回の制度改正は「単に暑いから気をつけよう」というレベルではなく、客観的な基準にもとづいた測定とマニュアル整備、教育体制の確立までを企業責任として明確にしている点がポイントです。
企業が講じるべき具体的な対策
熱中症対策の義務化に対応するためには、単なる注意喚起にとどまらず、職場環境や作業内容に応じた多角的な取り組みが必要です。ここでは、企業が実際に講じるべき対策を具体的に紹介します。
WBGT値の測定とモニタリング
職場での暑さ対策を始めるうえで欠かせないのが、WBGT(暑さ指数)の継続的な測定です。WBGT計を用いて作業場所の暑熱環境を常時把握し、数値が高くなった場合には、休憩時間の見直しや作業時間の調整といった具体的な対応を行うことが求められます。
定期的な水分・塩分の補給を促すルールの整備
熱中症の予防には、定期的な水分・塩分の補給が欠かせません。「のどが渇く前に飲む」「作業前後にも水分補給を行う」といったルールを明文化し、現場に掲示することで従業員の意識を高めます。塩タブレットや経口補水液の常備も有効です。
作業休止時間と冷却設備の導入
高温環境下での作業には、適切な休憩時間と冷却環境の整備が必要です。扇風機やミストシャワー、スポットクーラー、空調服の導入など、現場の実情に応じた設備投資を検討しましょう。また、気温が極端に高い場合には、作業を一時的に見合わせるといった柔軟な対応も求められます。
暑熱順化のためのスケジュール調整
新入社員や久々に現場に戻る作業者など、身体が高温環境に慣れていない場合には、「暑熱順化(しょねつじゅんか)」の期間を設けることが推奨されます。初日は短時間の軽作業からスタートし、徐々に作業量や強度を増やすなど、段階的な適応が必要です。
衛生委員会での継続的な議論と教育
安全衛生管理体制の中で、熱中症対策を継続的に見直すことも求められます。衛生委員会での検討や、従業員への定期的な安全衛生教育を通じて、現場ごとの課題や改善点を把握し、実効性ある対策を維持しましょう。
罰則と企業責任
2025年6月から始まる熱中症対策の義務化は、単なる行政指導にとどまらず、違反した場合には罰則の対象となる点に注意が必要です。もし企業が必要な対策を怠り、その結果として従業員が熱中症になるなどの健康被害が発生した場合には、労働災害として法的責任を問われる可能性も出てきます。
労働安全衛生法違反としての罰則
改正労働安全衛生規則に基づく措置を講じなかった場合、労働安全衛生法第120条により「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることがあります。特に、高温環境での作業時にリスク評価や緊急対応策を怠った場合、厳しく指導される恐れがあります。
安全配慮義務違反による民事責任
企業には、従業員の生命・身体を守る「安全配慮義務」が課されています。万が一、熱中症によって重篤な後遺障害が残ったり死亡事故が発生した場合、企業は損害賠償責任を問われる可能性がある点に注意しましょう。過去には、熱中症による死亡事故において数千万円規模の賠償命令が出された事例も報告されています。
労災認定による企業イメージの毀損
熱中症による労災が認定されれば、企業名が公表されることもあり、社会的信用の低下や採用活動への影響など、長期的なリスクにもつながります。また、従業員や家族からの不信感が広がれば、職場のモチベーションや定着率にも悪影響を及ぼしかねません。
法令遵守の観点だけでなく、従業員の安心・安全を守る企業姿勢は、組織全体の信頼やパフォーマンスにも直結します。本記事を参考に、自社で今からできる準備について確認しておきましょう。
まとめ
本記事では、2025年6月から企業に義務付けられる熱中症対策について、法改正の背景や要点、具体的な対応策、違反時の罰則までを詳しく解説してきました。
猛暑が常態化する中で、暑熱環境下で働く従業員の安全と健康を守ることは、企業にとって重要な責務です。法令に沿った対策を講じることはもちろん、現場の実情に応じた柔軟かつ実効性のある対応を継続することが、労働災害の予防と職場環境の向上につながります。
今後は、WBGT値の計測や休憩時間の設定、冷却設備の導入、安全衛生教育の強化など、多方面にわたる準備が求められます。熱中症対策の義務化は単なるルールの遵守ではなく、従業員を守り、企業の信頼を高めるための取り組みです。
法施行までに余裕がある今のうちから、現場ごとのリスクを把握し、計画的に対策を進めていきましょう。