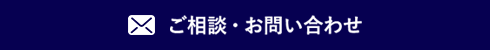コラム
水が蒸発する仕組みは?蒸発の身近な例や活用方法も解説
私たちが普段口にする水は小さな分子が集まってできています。この分子が他のエネルギーを吸収すると少しずつ気体となり、最終的にはほぼ完全に気体になります。この現象は「蒸発」と呼ばれます。
蒸発は私たちの周りのあらゆる場面で見られる現象であり、さまざまな分野の業界でも活用されています。本記事では、水が蒸発する仕組みや身近な例、工業分野で活用されているケースについて解説します。
なぜ水は蒸発するのか?
水は分子という小さな粒が集まってできたものです。分子は非常に小さなものなので目に見えませんが、水の状態は多数の分子が集まって作られているため、目で見ることが可能です。
しかし、この分子は他のエネルギーと組み合わさって状態を変化させます。水も外部のエネルギーを吸収することで、別の状態に変化します。その際、水は気体である水蒸気に変わります。この現象を「蒸発」と呼びます。
蒸発が起こると、分子はより活発に動き、水面近くの分子はその勢いで空気中に飛び出します。これが「水蒸気」です。水蒸気へと変わると分子同士の結びつきは離れてしまい、目では見えなくなります。空気が流れている環境では、液体の水が次々に蒸発し、最終的にはほとんどが気体に変わります。
『気化』や『沸騰』との違い
蒸発に似た現象に「気化」や「沸騰」がありますが、これらはそれぞれ異なる現象です。
気化は、液体が気体に変わる現象全般を指します。蒸発と沸騰は、気化現象の一部と言えます。
例えば、洗い終わった食器を食器かごに置き、時間が経っていくとともに乾きます。これは食器についた水分が、空気中のエネルギーによって水蒸気に変わっているためです。温度に関係なく進行するこの変化が蒸発です。
一方、沸騰は液体を加熱した際に、表面や内部から同時に気化が起こる現象です。これは蒸気圧と外気圧が関係しています。蒸気圧とは、同じ物質の気体と液体が共存しているときに気体が作り出す圧力です。温度が上がると、気体に変わる分子が増え、蒸気圧は強くなります。
水分の中には気泡が含まれていますが、気泡には内側から蒸気圧、外側から外気圧がかかっています。通常時は外気圧が強いため、この気泡はすぐにつぶれてしまいます。しかし、蒸気圧が強くなることで気泡がつぶれずに上昇し、大気中へと放出されることで「沸騰」となります。
蒸発の身近な例
「蒸発の仕組み」と言われてもとくにピンとこないかもしれませんが、実は私たちの生活において身近に発生しています。ここからは身近な例を3つ紹介します。
洗濯物の乾燥
洗濯した後の衣類は脱水しても濡れた状態です。これは繊維内に水分が残っていることが要因です。脱水した後に干されることで、太陽や空気中などの熱によって繊維内の水分が水蒸気へと変わります。その結果繊維内の水分がなくなり、衣類は乾燥していきます。
梅雨の時期のような湿度が高い状態だと洗濯物が乾きにくいのは、すでに空気中にも水分が大量に存在しているためです。衣類と大気中の水分が多いため、繊維内の水分が気体に変わるのが難しくなります。
コップの水が減る
蒸発は沸騰と異なり、温度に関わらず起こります。例えば、100℃以下でも水の表面は周囲から熱などが加わって気体となっていきます。空気が循環していれば、液体は徐々に蒸発し、最終的に水蒸気となります。
逆に空気の循環を抑えれば、コップの水は減少しません。たとえば、ラップで覆うとコップ内の水蒸気量が多くなり、蒸発は引き起こされなくなります。
ご飯粒が乾いて固くなる
お米は炊くことで水分が吸収され、一粒一粒がふんわりと柔らかくなり、食べられる状態にできあがります。炊飯器をイメージすると分かりやすいと思いますが、水とお米を釜に入れて熱を加え、お米が吸水することで膨張しています。
しかし、柔らかい状態をそのまま放置しておくと徐々に水分が蒸発していき、最終的にはほとんどの水分が失われます。その結果、お米は乾いて固くなってしまうのです。
工業分野でも活用されている蒸発の仕組み
蒸発は日常生活でよく見かける現象ですが、実はさまざまな分野の業界でも活用されています。たとえば、工業分野では以下のようなケースで使われています。
- 蒸発冷却
- 蒸気による殺菌
- 蒸発乾燥を用いた食品の加工
蒸発冷却
蒸発冷却は、工業設備で発生する熱を効果的に冷却するために使用されます。
代表的な例としては、発電所や商業施設に設置されているクーリングタワーがあります。クーリングタワーとは、使用した冷却水を冷やし、再び利用できるようにするための設備です。主に冷凍機や放熱が必要となる機械と組み合わせて利用されることが多く、発電所や工場の機械などを冷却する目的や高温の冷却水を低温にする目的で使われます。
クーリングタワーは、冷却水を外気と接触させることで一部の冷却水を蒸発させ、残りの冷却水の温度を下げています。水が蒸発する際に周りの熱を奪っていく気化熱の原理を利用しているのです。冷やされた冷却水は再度利用できます。
使用した冷却水を冷やして再利用することで、コストダウンや省エネルギーを実現するエコな設備としても注目されています。
蒸気による殺菌
蒸発によって発生する蒸気は殺菌や滅菌にも使われます。
殺菌・滅菌用として使われる「オートクレーブ」は、高圧蒸気滅菌器とも呼ばれ、高圧下で発生させた高温の水蒸気により、殺菌や微生物の滅菌をおこなう機器です。高温・高圧・水蒸気を使用することで、低温・短時間で効率的に殺菌・滅菌がおこなえます。
オートクレーブは、研究や医療現場、食品製造の現場など、幅広く使用されています。とくに医療現場では、人体に影響を及ぼさないように手術器具や医療器材を確実に滅菌しなければいけないため、非常に重宝されています。
蒸発乾燥を用いた食品の加工
食品を乾燥させて作られる食品フレークや粉末、ドライフルーツなどは、蒸発を用いて乾燥がおこなわれています。これらは蒸発乾燥技術を活用した機器を使って加工されます。また、陰干しや天日干しなど、自然のエネルギーを利用して乾燥させる方法で作られる食品もあります。
他にも、インスタントの味噌汁・スープなどで使用される「フリーズドライ」技術も蒸発乾燥の一例です。フリーズドライでは、食品の水分を氷から蒸気に急速に変化させる方法が取られます。高い温度を加えて蒸発させるほかの乾燥方法とは違い、食品の味や香り、栄養素が残りやすいのが特徴です。フリーズドライはお湯をかけるだけで食べられるものが多いので、非常食や宇宙食にも使われています。
まとめ
本記事では、水が蒸発する仕組みや蒸発の身近な例、工業分野で活用されているケースについて解説しました。
「蒸発の仕組み」と言われても普段はとくに気にならないですが、仕組みや原理を知ると私たちの生活においても身近に発生していることがわかります。また、蒸発の仕組みはいろんな分野の業界でも使われており、実は私たちの生活を支える大切な技術として活用されているのです。
今回紹介した例以外にも、蒸発の仕組みは多くの分野で活用されており、これからさらに技術が発展して利用方法が増えるかもしれません。仕組みや原理をさらに理解して、「あれって蒸発が使われているのでは?」と分析してみるとおもしろいかもしれないですね。