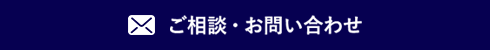コラム
PFAS規制とは?企業が受ける影響や備えておくべきポイントを解説
「PFAS(ピーファス)」は、炭素とフッ素の原子を含む化学物質の総称です。さまざまな種類が存在し、それぞれ異なる特性を持ちます。熱に強い、電気を通さない、汚れを防止することから、私たちの暮らしや産業のさまざまな場面で活用されています。
しかし、近年では人体の健康や自然への悪影響が懸念され、各国で規制強化の動きが加速しています。そのため日本の企業においても規制への対応が求められるようになってきているのです。
本記事では、PFASの規制の概要や規制によって企業が受ける影響、規制に備えて企業ができることについて解説します。
PFASとは?
「PFAS(ピーファス)」とは炭素とフッ素の原子を持つ化学物質の総称であり、1万種類以上が存在するとされています。種類によって特徴や性質も異なります。熱に強い、電気を通さない、汚れを防止するなど多くの性質があるため、私たちの暮らしや産業のさまざまな場面で活用されています。たとえば、私たちの生活の身近なものでは、以下のような製品に含まれています。
- フライパン
- 防水・撥水加工された衣類
- 撥水スプレー・防水スプレー
- 消火器(消火剤)
- 半導体
- 包装紙
- 防水服
- 化粧品
- 自動車のコーティング剤
- フロンガス
中でも、ペルフルオロオクタンスルホン酸やペルフルオロオクタン酸は、特に幅広い分野で使用されてきた代表的な物質です。
人体や自然に悪影響を与えるリスクが指摘されている
多種多様な製品に使用されている一方で、近年では人体の健康や自然に悪影響を与えることが指摘されています。以下は、懸念される人体の健康リスクの一部です。
- 発がん性リスク
- 甲状腺機能低下
- 免疫機能低下
- 高コレステロール
- ホルモンバランスの異常
- 胎児への悪影響
また、PFASは炭素とフッ素が非常に強い力で結びついているため、自然環境で分解されずに半永久的に蓄積されるという特徴も持っています。そのため海や土壌に長期間存在し、環境汚染の原因になっていることが指摘されているのです。
しかし、まだまだPFASに関する研究や分析は進められている途中で、「人体にどのくらいの悪影響を及ぼすのか」「健康に影響を及ぼす摂取量はどのくらいか」など現時点で確定していない点もたくさんあるようです。
日本で発生したPFAS汚染の事例
近年、日本国内でもPFASによる環境汚染が問題視されています。以下は日本で発生した問題の事例です。
東京都内全域を対象にした都の地下水の調査をおこなった結果、都内のすべての自治体のおよそ3分の1にあたる21の自治体で、国の暫定の目標値を上回るPFAS値が検出された。
参照:PFAS 東京都 地下水調査の結果判明 暫定目標値を超えて検出の自治体は|NHK 首都圏ナビ
ダイキン工業(本社・大阪市)の淀川製作所(大阪府摂津市)周辺でPFASが検出された問題を受け、京都大学の研究者らが大阪府を中心に約30自治体の1190人に血液検査をした結果、3割から指針値以上のPFAS濃度が検出された。
参照:米指針超えるPFAS、対象者3割から検出 京大研究者ら大阪で調査|朝日新聞
沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場周辺の地下水から高濃度の有機フッ素化合物PFOSが検出されている問題で、地下水が流れ出た海周辺の魚にも高濃度のPFOSが含まれていることが調査で分かった。
参照:普天間飛行場の地下水が流出する海 ハリセンボンから高濃度のPFOS 最大で全国平均の82倍 名桜・沖縄国際大が調査「食べるのは控えて」|沖縄タイムス
PFASの規制が進められている
現在、ペルフルオロオクタンスルホン酸とペルフルオロオクタン酸など一部の物質は、製造や製品への使用がすでに禁止されています。これらは「特定PFAS」と呼ばれていますが、この特定PFASに加えて今後さらに全体の規制が進められているのです。
国内の各省庁では、学識経験者たちとともにPFASに関する専門的な分析や規制の検討を進めているところです。先ほども触れましたが、日本各地で高濃度のPFASが検出される事例が確認されていることから、今後はさらに規制が強まっていくでしょう。
PFAS規制によって企業が受ける影響
国内の各省庁でもさまざまな取り組みがおこなわれていますが、今後は日本企業全体にPFASへの対応が求められるようになります。
とくに工業製品や機器から発せられるフロンガスなどにも、PFASの原料となるフッ素が含まれており、規制の強化により製造業の企業は大きな影響を受けるでしょう。製造や製品への使用において規制されるため、自社製品が規制対象になるか確認・分析したり、今までの製造工程を検討したりする必要が出てくるでしょう。
PFAS規制の予定
PFAS規制は、以下のように現在規制発動に向けて進んでいます。
| 日程の流れ | 内容 |
| 2023年2月 | 規制案の公表 |
| 2024年 | 協議、意見募集 法案起案 |
| 2025年 | 法案審議・採択 |
| 2027年 | 移行期間 18ヶ月後に規制発動 |
PFASに関する規制は、2027年を目処に生産や使用を禁止する規制が発行される流れとなっています。ただし、規制発行日から18ヶ月の移行期間が設けられているため、この移行期間が終了してからPFASの生産や販売、使用が禁止されます。
また、生活に欠かせない素材であっても制限対象となり、PFASは他の素材よりも優れた特性を有するために、代替品が存在しない用途が数多く存在します。そのため、代替品が見つかりにくい用途のために、18カ月の移行期間に加えて5年あるいは12年の追加猶予期間が設定されています。
PFAS規制に備えて企業ができること
PFAS規制への対策をしっかりとおこなわなければ企業が損失を受けるリスクがあります。以下のポイントをおさえて規制に備えましょう。
- 自社の製品や素材が規制対象になるかチェック
- 規制に対応できる方法を検討する
- 新しい素材の開発を考えてみる
自社の製品や素材が規制対象になるかチェック
まずは、自社の製品や素材が規制対象になるかチェックをおこないましょう。
製品におけるPFASの含有の有無は、原材料のチェックから始めることが重要です。原料・部品に規制物質の使用がないことが確認できれば、最終製品に含まれていないと考えられるでしょう。
ただ、PFASは製造工程のなかで使用されることもあります。もし原材料として使用されていない場合でも、製造工程で使用される器具にて使用されていると、最終製品への混入も発生するので注意が必要です。
規制に対応できる方法を検討する
自社の製品や素材が規制対象となった場合、規制に対応できる方法を考える必要があります。別の素材で代替できるものはないか、製造工程でPFASを利用しない方法はないかなど、自社の問題に対しての改善案を考えましょう。自社のみで難しい場合は、専門機関への相談も検討するとよいでしょう。
また、他社はどのように規制に対応しているかもチェックするのがおすすめです。同業種の企業の対策を知ることで、自社でも活かせる対策が見つかるかもしれません。
新しい素材の開発を考えてみる
簡単なことではありませんが、規制に対応できる新しい素材の開発を考えるのもよいでしょう。現在、脱PFASをテーマにして代替品となる素材の開発に取り組む企業が増えています。将来的な規制を見越して、代替物質の開発を検討するのも有効な対策です。
もちろん簡単なことではないので、開発には数年以上の時間がかかることが考えられます。しかし、新しい素材や代替品となる素材の開発を進めることができれば、新しい規制に対応できるだけでなく、市場をリードするきっかけにもなり得るでしょう。
まとめ
本記事では、PFASの規制の概要や規制によって企業が受ける影響、規制に備えて企業ができることについて解説しました。PFASは多種多様な製品に使用されている一方で、人体や環境への悪影響が懸念され、世界的に規制の動きが加速しています。
日本国内でも各省庁が対策を進めており、今後は日本企業全体が対策を求められるようになっていくでしょう。規制は企業にとって懸念する点でもありますが、しっかりと情報をキャッチアップし、定期的に対策方法を見直すようにしましょう。